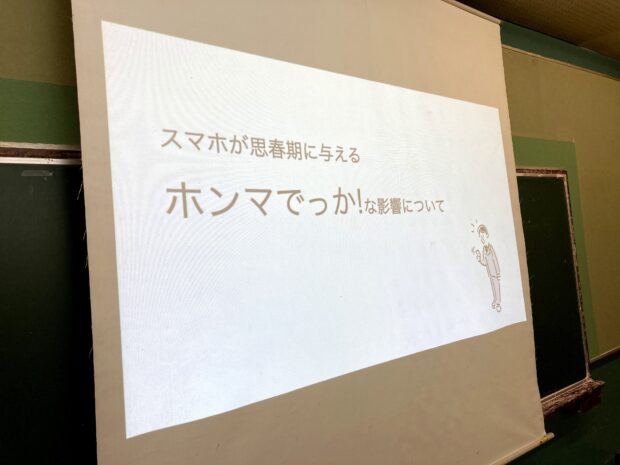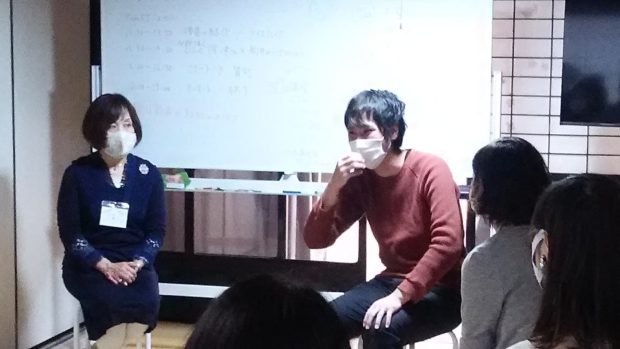こんにちは、スタッフの得津です。
2月18日(土)に、大阪市で子ども食堂を行われている団体さまへ、講演とワークショップをおこないました。
どのように子どもたちに関わっていけばいいかスタッフみんなで考える機会が欲しいとのご相談でしたので、子どもの発達と自尊感情について簡単に話した後、傾聴のワークショップとケーススタディをしました。
私たちも委託事業として、中学生向けの居場所作り事業をおこなっています。ケーススタディはここにくる子どもの話を出しました。あわせて実施したワークショップも紹介しました。2時間でしたが、あっという間に過ぎていきました。
今日は、子ども食堂を運営されているかたへ向けて、クオリテイを上げるためのアドバイスを、講演内容の中からさせていただきます。
普段受ける講演でしたら、こんなことはいたしません。
ちゃんと時間やお金を割いてきてくれた方にお伝えしたいからです。
でも子ども食堂は運営者の持ち出しでされていることが多いです。
学びたくても費用が・・・というケースも多いでしょう。
だからこそ、子ども食堂の運営については事例や考え方はどんどんオープンにして、どなたでもマネできるようにすればいいとぼくは思うので、講演で話したことを今日は公開いたします。
運営者にお伝えしたいのは
1、運営している場所がどんな場所かハッキリさせること
2、20分でもいいから毎回スタッフでふり返りをすること
この2つです。
まず1番、「運営している場所がどんな場所かハッキリさせること」についてです。
子ども食堂は、いろんな子どもも大人も来ます。何度もくる人もいれば、初めてくる人もいます。
中には、自分たちが運営する子ども食堂がどんな場所なのかを知らない人だっています。
だからこそ、自分たちが運営する子ども食堂はどんな場所なのか。ここで過ごす決まりは何か。
これらをはっきりさせて伝えることが必要です。
私が運営している場所では、「みんなが笑顔でいられる関係になれる場所」としています。これは子どもたちと一緒に考えました。うちでは毎回くる子どもが決まっているので、「ここをどんな場所にするか」一緒に考えることを最初から決めていました。
ですが、開設してすぐに「ここをどんな場所にしたい?」なんて聞きません。
それは子どもにとってすごいプレッシャーです(笑)
オススメは、4・5回ほど経って子ども同士が打ち解けてきたなと思ったころです。この時期になると、子ども自身があなたの子ども食堂で過ごした思い出もあります。これを考える材料にすれば、大人がひっぱっていく「お飾りな目標」にはなりません。
それまでは仮の決まりやルールを出しておいて、「〜月には、どんな場所にしたいかみんなで考えるよ」と子どもに伝えればOKです。
できあがった決まりやルールは折に触れて子どもに伝えましょう。毎回初めての人がくる可能性があるなら、しつこくても毎回あなたの子ども食堂がどんな場所か伝えるようにしてください。うちの居場所でも新しい子どもが来たら必ず伝えています。
これは子どもが居場所に馴染みやすくするためでもありますが、大人のためでもあります。意外と大人の方が忘れていることが多いですし、新しいスタッフも何をすればいいか分かりやすいので、しつこくても伝えましょう。
次は、2番。「20分でもいいから毎回スタッフでふり返りをすること」です。
ふり返りは、次はどうすればいいかを考える貴重な機会です。少しのふり返りが居場所のクオリティを高めてくれます。疲れていても、ここは踏ん張ってください。
ふり返る項目は、
1、その日にした活動の改善点を出す
2、子どもの態度や発言から気になる点や心配な点はなかったかを出す
3、対応にこまった場面をどうすればいいかみんなで考える
主にこの3つです。
特に2と3が大事です。
子どもの様子や、困った場面をふり返って、次にどうするか決めることで、スタッフが次のチャレンジ目標を持ちます。これはスタッフ一人ひとりの意欲を高めますし、スタッフが同じ方向を向いて居場所を運営することにつながります。ただただ子どもの文句を言い合うだけの場は、イヤですよね。やっぱり。
だから、スタッフでふり返る場をつくって、次は何をするかみんなで決めてください。
この積み重ねが、あなたの子ども食堂を大きく成長させます。
出た意見は、ワードで記録してスタッフがいつでも見れるように記録・管理しています。
どんな形であれスタッフが参照できることが重要です。その日これなかったスタッフが、次に参加するときにどんなことがあったか知っておけば、参加もスムーズです。
例えば、webでふり返り内容を管理することもできますが、スタッフの年齢層によってはwebが合わないこともあります。そんな時は、紙でまとめたことをファイルしておいて子どもが来る前に前回のおさらいをしておくだけでも随分違います。
最後に
子ども食堂を運営されている皆さまには本当に頭が下がります。基本的にはボランティア精神でやってるところがほとんどだと聞きます。立派だと思います。
ただ、全国に300箇所以上が開設され、今尚その普及が進んでいる現状にあって、そろそろ質の議論がされ出すころではないかと感じています。
「子どものことは何もわからんけど、ご飯つくってあげるくらいなら私にもできる」
この記事が、そんな気持ちでスタートされた運営者のアドバイスになれば幸いです。
運営についてお悩みでしたら、私たちの実例も紹介しますので是非一度ご相談ください。
幸せな子ども時代を一緒につくっていきましょう。