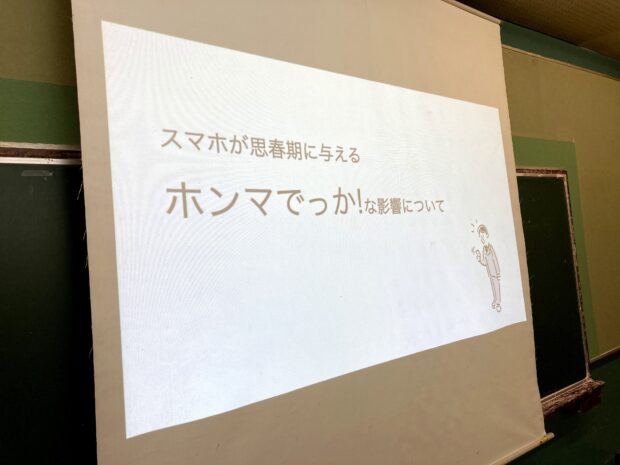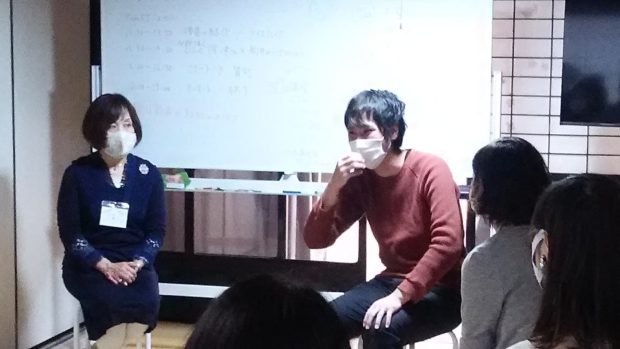2月5日は、「思春期の子どもとの関わりかた講座」の第2回を開催しました。
テーマは失敗を怖がる子どもの気持ち。
学校では特にそうですが、子どもたちが授業中に意見を発表するのを怖がったり、間違えたらどうしようと思ったりする様子が見られます。
お家でも似たようなことがあるらしく、保護者さんのお悩みもちらほら。
会は、代表の田中とがTRY部に通う子どもの様子や考え方を参加者の意見や質問を受けながら進行しました。
子どもがどうして失敗を恐れるのかというトピックから損を避ける子どもの心理になり、子どもが宿題をしないのはどうしてかという話題にうつりました。
子どもが宿題をしないのは、見通しがもてないからだそうです。
どうして宿題をするのか、お家に帰ってどんな手順で宿題をするのかがわかれば子どもは宿題をすると代表は話します。
たしかに、自分が教員をしていた時も家に帰っていつ宿題をするのか決まっている生徒は毎日宿題を出していました。お家に帰ってカバンを部屋に置いてすぐやる子もいれば、友だちと遊んで19時になるまでにすると決めている子もいました。
子どもに何度言っても宿題をしないとお悩みの保護者は、一度子どもといつ宿題をするのかルールを決めてみるのはいかがでしょう。
子どもの学年が上がるにつれて、こんな話をする場を持つのは難しいです。
ですが、そこは無理にでも時間を作り、どうして宿題をしてほしいと思っているのか、いつ宿題をするのかを子どもと話し合って決めてみませんか。
話し合う上で大事なのは、責めるような口調にならず子どもに考える余地を与えることです。こちらは帰ってすぐに宿題をして欲しいと思っていても、子どもが友だちと遊ぶ約束がお決まりになっているとそれは難しい。どの時間が使えるのか、どの場所でやるのかなど、子どもの意見を聞きながら決めていきましょう。
話はそれましたが、今回の講座では話し合うだけじゃなくケーススタディも行い、インプットしたことをどう実際に活かしていくかの練習をして終わりました。
次回の開催は三月。小5〜高3のお子さんを持つ保護者だけの講座です。
子どもが思春期や反抗期をむかえ、どうコミュニケーションを取ればいいかお悩みの保護者さんはぜひ一度、お越しください。
参加された保護者さんはいつもすっきりした顔でお帰りになっていますよ。