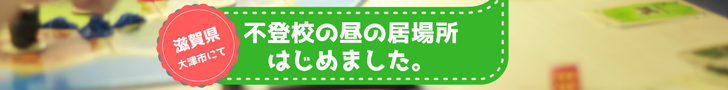「子どもが学校へ行けなくなってしまった」
こんなとき、あなたはどうするだろうか?
なんとか学校へ行かせようとする。
カウンセリングへ通わせる。
じっくりと待つ。
いろんな方法があるだろう。
ネットには情報は溢れ、知恵袋にも不登校に関する様々な質問があがっていきている。
不登校経験者として、不登校の子どもたちに関わるものとして、思うのだ。
大事なのは、カウンセリングや医者ではなくって、ピアノの調律師だと。
そもそも、どうして不登校になるのだろう?
どうして、学校へ行けなくなるのだろう。
理由は、様々だ。
子どもによって、いろんな理由があり、たくさんの背景がある。
一概には言えないけれど、実は、物事は、そう単純ではないのだ。
不登校の原因として、“いじめ”や“先生が合わない”なんて理由は、それほど多くない。
“先生がキライ”というのはあっても、それがキッカケになっただけで、全ての原因になるわけじゃない。
先生が嘆いているのを聞いたことがある。
「不登校になった子が久しぶりに学校へ来ると、すごく楽しそうに、別に他の子と違わない感じで振る舞っているんです。
なのに、やっぱり、数日たつと来なくなっちゃう。どうしてなんでしょう?」
ハタから見ると、ん?この子は、ただ休みたいだけの、ただのずる休みじゃないのかしらん、と思ってしまうこともあるだろう。
楽しそうに学校で過ごしているのに、行きたくないというのは、親や教師にとってみると、ほんとうになにがどうなっているのか、ちんぷんかんぷんのように思える。
お家を訪ね、「大丈夫か?ガンバって学校へおいで!」と励ます熱心な先生もいらっしゃるけれど、僕から言わせてもらうと、とんだお門違いだ。
不登校には、大きく分けると2種類いる。
“行きたい子”と、“行かない子”。
前者は、学校へは行きたいと思っているけれど、どうしてか、自分でもわからないけれど、行けない。
後者は、もうただ学校が嫌いだったり、学校が合わない、学校に行く意味がわからない、という子だ。
不登校と呼ばれている子の多くは、前者だ。
学校へ行かないとだめなことはわかっていて、そこまで学校が嫌いというわけじゃない。
でも、“行けない”のだ。
“行かない”のではなく、“行けない”のだ。
もう、ただ、ほんとうにズル休みのように思ってしまうけれど、ちがう。
本人がなによりツライ。
自分は、なんとか行こうと思っていて、「今日こそは!」と意気込んだものの、いざ行くとなると、足がすくむ。
お腹が痛くなる。頭が重く感じる。
励ましたところで、行きたくても本人は行けないのだ。
骨折している人に「ガンバって歩くんだ!」と言うようなもので、本人としては、もう、どうガンバったら良いのかもわからない。
うちの教室に通う生徒で、学校に行かないでずっと家でゲームばかりをしている中学生がいる。
そんな彼に、自己評価アンケートをとったところ、自己採点がすごく低かった。
理由を聞いてみると、「学校へ行っていないから」だと言う。
もしかしたら、この子は学校なんてどうでもいいと思っているのかもしれないなと思っていたけれど、そうじゃなかった。
学校に行けないことを気にしていて、心の中では「行かないとダメだよなぁ」と思っている。
サボっているのではなく、ただ、ただ純粋に、“行けない”のだ。
僕としては、学校に戻る、学校へ行けるようになることが、ベストな選択だとは思わない。
楽しく学校へ行けるようになれば、それはきっとベターなんだけど、全員がそうなるのはやっぱり難しい。
不登校になり、学校へ行けないと悩んでいる子が、楽しく生きられる、毎日を気持ちよく過ごせるようになったらそれでいい。
今の学校に通い続ける、フリースクールへ行く、ホームエデュケーションをおこなう。
選択は、その子が決めたらいい。
学校へ行けなくて苦しんでいる状況から抜け出すために、必要なのが調律師だ。
僕がまだ小学生だった頃。
大阪の実家にはピアノがあって、たまに知らないおっちゃんが来ていた。
親に聞いてみると、「ピアノの調律をしているの」と、教えてもらった。
オーケストラに入って、バイオリンを弾いていたときも、はじまる前には音合わせがあった。
調律、いわゆる、チューニング。
楽器は、音が変わりやすいから、はじめにチューニングをおこなう必要がある。
1人でも変な音を奏でるものがいたら、オーケストラでの演奏も聴くに堪えないことになってしまう。
学校でも同じ。
学校では、みんなと同じ音を出すことが好まれる。
違う音を奏でる者がいたら、みんなの迷惑になってしまう。
同調圧力のようなものをイメージすると、わかりやすい。
自分が気持ちよく、みんなと同じ音を出せるなら、それでいい。
でも、そうじゃない場合が問題だ。
みんなの音と合わすのが苦手、自分の音を出したい子にとっては、学校はとてもシンドイ。
僕は、学校では、誰にも理解されなかった。
ずっと“異端児”だった。
同級生にも先生にも理解されず、変なヤツ、で生きてきた。
みんなと同じ音を出すこと拒み、自分の音を出すことを貫いてきた。
自分で切り開くしかなかった。
しかし、誰にでも、こんな孤高のような生き方ができるわけじゃない。
不登校になる子は、同調圧力に苦しみ、いつの頃からか自分の音が出せなくなる。
なんとかして、みんなの音と合わせようとするあまり、気がつけば、自分の音を見失ってしまう。
先生が言っていた、不登校の子がたまに学校へ行ったとき、楽しそうに見えるのは、もう、ただ、必死で、みんなの音に合わせようとしているから。
だから、学校から帰ってきたら、しんどくなる、翌日から行けなくなる。
カラオケでずっとキーの高い曲ばかりを歌っていると喉を痛めるように、周りに合わせていると、しんどくなってしまう。
今、僕たちは、不登校の子たちに向けて、個別面談や教室運営をおこなっている。
と、言うと、「ああ、不登校支援なんですね」と言われるんだけど、別に助けてあげているというつもりでやっているわけではない。
不登校の子は、疲れていることはあっても、別に弱っていることはない。
(もちろん、中には精神に不調をきたしている子もいる)
僕たちがやっていることは、ただ、その子のチューニングをしているだけだ。
面談で2時間ほど話すと、その子のどこが、音程が合っていないのかがわかる。
不登校の子たちは、弱っているのではなく、うまく自分の音が出せないだけ。
話を聞き、どんな音を出したいのか、なぜ音が出せないのか原因を探す。
まるで、何度も、何度も鍵盤を叩きながら、音を合わせるピアノの調律師のように。
学校へ数ヶ月行けなくなってしまった高校生がいた。
彼は、とても優秀で、勉強が良くできた。
進学校に入り、次第についていけなくなった。
面談で彼と話をしていて、僕は1つ腑に落ちないことがあった。
親御さんからは、「うちの子、勉強が苦手で学校へ行けなくなったのです」とご相談を受けて、本人と話していのだけれど、どうもおかしい。
どう考えても、彼は勉強が嫌いな子ではないのだ。
好奇心も旺盛で、意欲も高い。
学校へ行けない理由に、“勉強”がどうして入ってくるのかがわからなかった。
詳しく聞いていくと、やっと、答えが見えた。
彼は、“自分のやり方で勉強がしたい”と思っていた。
自分の音を出したいものの、“課題”という名のもとに、毎日膨大な量の宿題がでる。
自分のやり方など関係なく、うむを言わさず課題が出される。
なんとか耐えていたものの、ついに、彼のカラダと精神は、悲鳴をあげた。
僕は、学校で異端児として生きてきた。
だからこそ、僕ができることがある。
自分の音が出せないならば、自分の音が出せる環境を自分で作ればいいのだ。
彼に聞いてみた。
「先生に話して、課題は出さないでもらおう。授業中に当てられることも禁止にしよう。それだったら、学校に行けるかい?」
「うん。それなら、大丈夫だと思う」
「よし!でもね、課題も予習もしない代わりに、自習ノートを出そう!それで先生に許してもらえないか確認をとるんだよ。そして、1つ。テストではちゃんと点数取ろう!自分のやり方で、キチンと結果を出そう」
「うん。大変そうだけど、ガンバる。そのほうがきっと楽しそう」
別に、無理をして、我慢して、学校へ行く必要なんてない。
学校へ行けない理由があるのなら、その原因を消せばいい。
学校はマジョリティ向けのサービスで、それに合わない子もいる。
僕がそうだったように、彼もまた、学校という環境には馴染まなかった。
でも、だからといって、じゃあ学校を辞めましょう、という話ではなくて、自分が生きやすいように、交渉すればいいのだ。
近頃、ふと思うことがある。
実は、不登校というのは、それほど難しい問題ではないのでは、と。
医者にかからないといけない子もいるし、精神的に参ってしまって時間がかかる子もいる。
一概に、“簡単”とは、もちろん言えないのだけれど、不登校の子と接していると、思う。
不登校になる子も、学校へ行っている子も、それほど大差はない。
残念ながら、他の子よりも音を出すのが苦手だったり、同じ音を出すのがしんどいだけなんだ。
僕たちは、そんなちょっとうまくいかない子たちにたいして、面談や教室(TRY部)をおこなっている。
自分の音を知るために、有料の面談をおこなう。
みんなに合わせるのではなく、自分の音を出せるように、教室をおこなっている。
自分の音を見つけ、自分が心地よい音色を奏でられる安心出来る空間で、子どもたちは少しずつ、自分を取り戻していく。
僕は思う。
不登校の子に必要なのは、支援ではなく、ピアノの調律師かもしれない。と
お問い合わせは、info@dlive.jpまで。