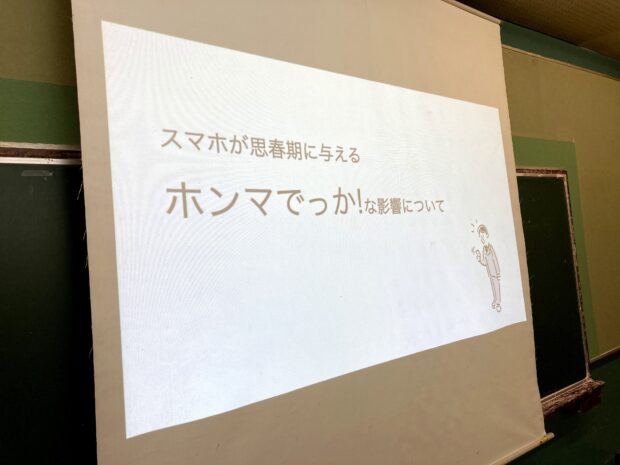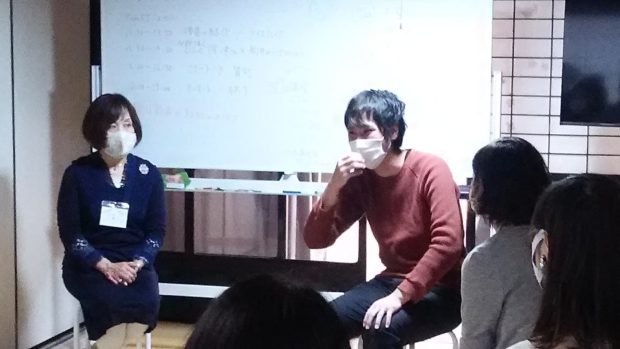スタッフの得津です、こんにちは。
12月4日(日)、京都の「学び舎 傍楽」さんと協力して「子どもの自信を育てたいあなたのための読書会」を開催いたしました。参加者みなさんがざっくばらんに話せる時間をつくりたかったので、定員を10名と普段よりも少ない人数にしての開催でした。
当日は雨の降る天気でしたが、お申込みいただいたみなさまにご参加いただきました。
告知の情報を見られた方にとっては。「子どもの自信白書の読書会って何をするの?」と疑問に思われている方も多かったと思います。僕自身もD.Liveとして初の試みだったので、どうしようかなぁとギリギリまで頭をひねっておりました。あれやこれやと考えてはいましたが、参加者の方には「とてもよかった」と満足いただけました。
終わってみて思うのは、この白書は子育てや教育の話をひろげるイースト菌なんだと気付きました。
パンを作るときに、かならず小麦粉にイースト菌をいれてパンを膨らませます。
それと同じく、子育てや教育について話し合う場をつくるときに「子どもの自信白書」を使うと、みるみる話が膨らんでいったんです。
今回は、「子どもが本当にやりたいことを見つけるために大人ができることって何だろう」というテーマで2時間おこないました。
「高垣先生のページに、『服だって、3・4着試着するのに、自分自身のこともあれこれ試してみないとわからないよね』っていう言葉、ほんとその通りだと思って」
「団体紹介のページで、大人が夢をもつことが大事ってあるのが、確かにそうだなぁって思いました。一回目は見逃していたんですが、この言葉いいですよね。」
などなど、白書の文章を出発点にどんどん話が膨らんでいきました。
・現状の学校教育でできることはいったい何か
・子どもは旅をすることで変わっていく
・「勉強って何のためにやるの?」という子どもの疑問をどう受け止めるのか
・親の気持ちの伝え方
たくさんのトピックが自然に生まれていき、中には、お家の人のことを思い出し涙される方もおられました。
話を広げていくためには、イースト菌のような「触媒」が必要です。参加者同士の反応を促すものがないと、「さあ話しましょう」と言われても参加者としては話しにくいのが正直なところです。
では、何が触媒になるのか。例えばワークショップだったらテーマや問いが触媒にあたりますし、ゲストをお呼びした講演会なんかもそうです。主催の「こんなこと考えて欲しい、話して欲しい」という反応を生むために、たくさんの触媒になりえるものがあります。
その中で、「子どもの自信白書」は子育てや教育について話をひろげる触媒としては、手軽で使いやすい冊子だなと手前味噌ながら思うわけです。
イベントを終えた後、スタッフ同士で「居酒屋で喋るのと何が違うのか?」と話し合い、自分も頭を悩ませました。何が違うんだろう。しかし、話の起原をたどってみればそこにはやっぱり「子どもの自信白書」があり、白書からたくさんの問いが生まれました。
探求型の学習というのは、そういうものみたいですね。2016年1月に、ファシリテーショングラフィックを学びにいったときに講師の方がおっしゃっていました。探求的な学びというのは、一つの問いからある参加者は答えを見つけ、ある参加者はまた別の問いを持つ。それがまた探求する姿勢のエンジンになるそうです。
今回の参加者の感想の中に
そもそもやりたいことを見つけないといけないのか、という自分にとっては新しい疑問だったりを知れたり、「たしかにそうだな」と、もっと自分で深めたい点を見つけられたのは、自分にとって収穫でした
という意見があり、「居酒屋でのおしゃべりとは違うな」と確認できました。
読書会の今後の予定ですが、
1月は一般社団法人コアプラスさんとの共催でさせてもらいます。こちらおかげさまで、すでに定員となりました。
2月は滋賀での開催を予定しております。
私たちとしてはこれで終わりではなく、今後、気軽に子どもの自尊感情について学び、話せる場をつくるために子どもの自信白書を使った読書会を行っていきたい気持ちです。
その上で、コアプラスさんと共催でさせていただくように、関西圏の子育てサークルや教育系団体、子どもについて学ぶ場を作りたい人たちと一緒にさせてもらえればと思っております。
特に、話を広がりにマンネリを感じている人にとっては、「子どもの自信白書」という話を広げるイースト菌があります。
子どもの自信白書を使った気軽な読書会や、研修、講演のご依頼は info@dlive.jp
今の子ども、特に中高生はどんな気持ちで日々を過ごしているのか。大人はどう関わっていくのか、ぜひ一緒に考えていきませんか。
ご連絡お待ちしております。